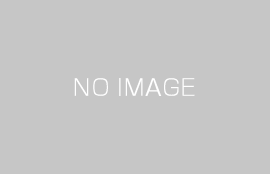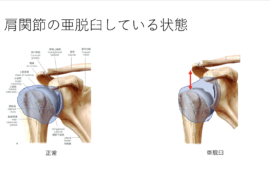本日は臨床で悩む「痙縮」の病態について論文を和訳しながら考察していきたいと思います。
脳卒中後の患者様にも分かりやすく注釈を入れますので、ぜひご参考下さい。
Pathophysiology of Spasticity: Implications for Neurorehabilitation
Carlo Trompetto,1 Lucio Marinelli,1 Laura Mori,1 Elisa Pelosin,1 Antonio Currà,2 Luigi Molfetta,1 and Giovanni Abbruzzese1
1 Department of Neuroscience, Rehabilitation, Ophthalmology, Genetics, Maternal and Child Health, University of Genoa, Largo Daneo 3, 16132 Genoa, Italy
2 Department of Medical-Surgical Sciences and Biotechnologies, Sapienza University of Rome, Polo Pontino, Via Firenze, 04019 Terracina, Italy
Correspondence should be addressed to Laura Mori; morilaura@hotmail.com
Received 23 April 2014; Revised 11 July 2014; Accepted 9 September 2014; Published 30 October 2014
LINK→https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4229996/pdf/BMRI2014-354906.pdf
痙縮の病態整理: 神経リハビリテーションへの影響
1. はじめに
痙縮(spasticity)は伸張反射障害であり、筋肉の緊張が増加し、特に速い伸張運動で顕著になります。これは上位運動ニューロン症候群(UMNS)を引き起こす損傷に関連する一般的な結果です。
本論文の主な目的は以下の通りです。
1. UMNSの一部としての痙縮の臨床的特徴を説明すること。
2. 健常者における筋緊張のメカニズムを説明すること。
3. 痙縮が脊髄での感覚入力の異常な処理による伸張反射の過剰に起因することを示すこと。
4. UMNS患者における筋短縮や線維症(固有の筋緊張)による筋過緊張もまた原因であることを示すこと。
5. 上位運動ニューロンを損傷する病変が伸張反射を制御する脳の抑制性および興奮性入力のバランスを乱すことを示すこと。
6. 上位運動ニューロン機能不全によって引き起こされる脊髄での伸張反射興奮性の変化を記述すること。
7. UMNS患者の四肢の動員が痙縮と固有の筋緊張の両方を予防・治療する上で重要であることを強調すること。
2. 定義と臨床的特徴
痙縮の核心的な特徴は、伸張反射の過剰です。その結果として、受動的に伸張された筋肉または筋群の抵抗が速度依存的に増加します。1980年、Lanceは次のような定義を発表しました(頻繁に引用される定義です):
「痙縮とは、上位運動ニューロン症候群(UMNS)の一要素として、伸張反射(筋緊張)の速度依存的な増加と腱反射の誇張により特徴付けられる運動障害である。」
この定義は、痙縮がUMNSの一部であることを強調しています。
速度依存性に加え、痙縮は長さ依存性の現象でもあります。例えば、大腿四頭筋では筋肉が短いときに痙縮が強く、長いときには弱くなります。このメカニズムは「折りたたみナイフ現象」の背後にある一因と考えられています。膝を曲げる際、最初は(筋肉が短いとき)大きな抵抗が感じられ、その後、大腿四頭筋が伸びると抵抗が突然消失します。一方で、上肢の屈筋や足関節の伸筋では、筋肉が長いときに痙縮がより強くなる場合があります。
痙縮は上肢の屈筋(指、手首、肘の屈筋)および下肢の伸筋(膝および足関節の伸筋)でより頻繁に見られます。しかし、いくつかの例外があります。たとえば、前腕の伸筋に痙縮が優勢である患者も観察されています。
痙縮は、筋肉を速く伸ばすと筋肉が勝手に収縮する。速く伸ばす際に、筋肉の長さに余裕がないとすぐに反応してしまう。
痙縮が強い足で速く歩いたり、力強く踏むと硬くなるのはこれが理由です。
3. 健常者における伸張反射と筋緊張
健常者において、伸張反射は筋紡錘からのIa求心性線維と、これらが起始する同一の筋肉を支配するα運動ニューロンとの間の興奮性結合によって媒介されます。筋肉の受動的な伸張は筋紡錘を興奮させ、Ia線維が発火し、主に単シナプス性経路、また少数の多シナプス性経路を介してα運動ニューロンに入力を送ります。これにより、α運動ニューロンは筋肉を収縮させる運動信号を送ります。
安静時の健常者における筋表面の筋電図(EMG)記録によると、通常の臨床的な筋緊張評価で使用される速度(60度~180度/秒)で実施される受動的な筋伸張では、伸張反射による筋収縮が発生しないことが示されています。たとえば、肘を伸ばす動作中に肘屈筋の筋電図を記録した場合、通常の評価速度では上腕二頭筋に伸張反射は観察されません。伸張反射が発生するのは、200度/秒を超える速度の場合です。したがって、健常者において筋緊張は伸張反射が原因ではありません。筋緊張は完全に生体力学的要因によるものです。
関節を速く動かしても、筋電図上で収縮が出現するほどの反応が出ないのが通常。これよりも運動に応じて必要な時に必要な分だけ勝手に筋肉が適切に働いてる。
4. 痙縮患者における筋緊張: 誇張された伸張反射
健常者とは異なり、痙縮患者では安静時(完全にリラックスした状態)でも、伸張された筋肉のEMG活動と伸張速度の間に正の線形相関が見られます。この速度範囲は臨床的評価で使用されるものと同様です。受動的な伸張が遅い場合、伸張反射は小さく(振幅が低い)、筋緊張は比較的正常またはわずかに増加していると感じられることがあります。しかし、筋肉を速く伸張すると、伸張反射が増大し、検査者は筋緊張の増加を検出します。したがって、痙縮は伸張反射の誇張によって引き起こされます。
痙縮は速度依存的であるにもかかわらず、表面筋電図記録によると、伸張が維持されている場合(速度=0)でも、筋肉は収縮し続ける場合があります。つまり、痙縮は古典的には動的な現象と考えられていますが、動的条件下での伸張反射による収縮後にも等尺性の持続的筋収縮が見られる場合があるのです。
伸ばした状態で動かさなくても収縮が続いている人もいる
5. 軟部組織の変化: 固有の筋緊張
痙縮は、UMNS(上位運動ニューロン症候群)患者における筋過緊張の速度依存性の要因です。しかし、これらの患者における筋過緊張は、痙縮だけでは説明できない複雑な現象であることを強調する必要があります。
動物研究では、短い位置での筋の固定が筋線維数を減少させ、筋肉内の結合組織の割合を増加させることが示されています。このような変化は、固定化の非常に初期段階で現れ、筋肉の受動的な動きに対する抵抗を高めるとともに、筋紡錘の静止時の発火および伸張に対する感受性を増加させます。同様の適応がUMNS患者の筋拘縮においても生じていると考えられます。
UMNS患者では、筋拘縮が筋過緊張に大きく寄与します。したがって、筋過緊張は2つの要素に分けることができます。伸張反射による過緊張(これが痙縮に対応)と、筋拘縮による過緊張(これが「非反射性筋緊張」または「固有の筋緊張」と呼ばれます)です。痙縮とは異なり、固有の筋緊張における受動的な動きに対する抵抗は、動きの速度とは関係がありません。しかし、臨床環境において、筋繊維化が筋短縮を伴わない場合、反射性および非反射性の筋過緊張を区別することは難しい場合があります。
バイオメカニカルな測定と筋電図(EMG)記録を組み合わせることで、この区別を支援できます。ただし、これら2つの筋過緊張の要素は密接に関連している可能性が高いと言えます。筋拘縮による筋肉の伸展性の低下は、「どんな引張力も紡錘により容易に伝わる」状況を作り出し、痙縮を悪化させる可能性があります。
麻痺した筋肉は短くなるし、結合を強くする。なので、早い段階でできる限り動かすこと。これは低周波を使ってもいい。そしてなるべく、筋肉は長い状態をキープするように。
6. 痙縮患者における伸張反射の誇張は脊髄での感覚入力の異常な処理による
理論的には、痙縮患者における伸張反射の誇張は、以下の2つの要因によって引き起こされる可能性があります。
1. 筋紡錘の興奮性の増加。
2. 筋紡錘からの感覚入力の脊髄内での異常な処理による、α運動ニューロンの過剰な反射的活性化。
古典的なネコの除脳研究では、γ運動ニューロンの過活動とそれに伴う筋紡錘の過興奮性が、過緊張の原因として関与していることが示されています。一方で、人間を対象とした研究では、紡錘運動系の機能障害が伸張反射の誇張にほとんど寄与していないことが示唆されています。そのため、現在広く受け入れられている見解は、痙縮は筋紡錘からの正常な入力が脊髄内で異常に処理されることによるものであるというものです。
痙縮の速度依存性はIa求心性線維の速度感受性に起因すると考えられます。しかし、いくつかの研究では、筋紡錘からのII群求心性線維も痙縮に関与しており、これらが多シナプス経路を介してα運動ニューロンを活性化することが示唆されています。II群求心性線維は長さ依存性であるため、痙縮患者においては、動的伸張反射の後に見られる等尺性の筋収縮にも関与している可能性があります。
筋肉が伸びるとその感覚が脊髄に「伸びたよ」という情報が入る。これは脳卒中患者でも正常であるが、脊髄内で伸びた感覚をうまく処理できない。正しい情報は入ってる、でも対処が出来ない状態。
7. 上位運動ニューロン症候群: 痙縮はその一部である複雑な病態
脳卒中や上位運動ニューロンを損傷する外傷の後、筋力低下や巧緻運動能力の喪失が即座に顕在化します。他の徴候として、筋緊張低下や深部腱反射の減弱または喪失が挙げられます。これらの徴候は「上位運動ニューロン症候群(UMNS)」の陰性徴候として知られています。その後、筋過活動を特徴とする他の徴候が現れます。これらには以下が含まれます。
• 痙縮
• 深部腱反射の増強(腱反射の誇張)
• 振戦(クローヌス)
• 伸展性痙攣
• 屈曲性痙攣
• バビンスキー反射
• 陽性支持反応
• 共収縮(cocontraction)
• 痙性ジストニア
• 関連反応(associated reactions)
これらの徴候は陽性徴候と呼ばれます。その中で、陰性徴候と同時期に出現する唯一の徴候はバビンスキー反射です。
伸張反射の過興奮性は、痙縮、振戦、深部腱反射の増強を引き起こします。屈曲性反射の生理的な引き抜き反応の過剰な興奮性は、脊髄損傷後によく見られる下肢の屈曲性痙攣を引き起こします。原始反射(出生時には存在するが、発達に伴って抑制される反射)の再出現は、バビンスキー反射や陽性支持反応の原因となります。
一方、共収縮や関連反応は脊髄反射に依存しません。したがって、これらは遠心性の現象です。また、痙性ジストニアも遠心性の駆動に依存していると考えられています。
共収縮(Cocontraction)
共収縮とは、関節を取り囲む拮抗筋(例えば、手関節の屈筋と伸筋)が同時に収縮する現象を指します。健常者では、大脳皮質の随意的な出力が拮抗筋を支配する運動ニューロンを抑制(相互抑制)することで、随意的な筋収縮が可能になります。しかし、UMNSでは、随意運動命令中に相互抑制が失われるために共収縮が生じます。この現象はUMNS患者における最も障害を引き起こす筋過活動の形態であり、力の生成や運動を妨げます。
関節を動かす際に、動かした方向と逆の方向も同時に筋収縮が起こってしまう。
関連反応(Associated Reactions)
関連反応とは、非麻痺側の筋肉の随意的な収縮やあくび、くしゃみ、咳などの非随意的なイベント中に、麻痺側の筋肉が非随意的に動く現象を指します。たとえば、片麻痺患者の歩行中に、肘の屈曲や腕の挙上が見られることがあります。
痙性ジストニア(Spastic Dystonia)
痙性ジストニアは、安静時に筋肉または筋群の持続的な収縮を指します。筋肉を弛緩させることが困難であるという相対的な障害として説明されます。痙性ジストニアは、安静時の姿勢を変化させ、片麻痺姿勢(上肢が屈曲し内転、下肢が伸展)を形成する要因となります。この現象は筋伸張や長時間の伸張により誘発される場合がありますが、伸張を継続することで減少することもあります。痙性ジストニアは、異常な脳の下降性入力パターンによって媒介される遠心性現象であると広く認識されています。
意識とは別に筋肉が硬くなることがある。これは筋肉を伸張することで抑制することもできる。
8. 伸張反射に対する脳の影響: 動物研究
1946年、MagounとRhinesは、延髄の錐体直後に位置する延髄網様体の腹内側部(ventromedial bulbar reticular formation)に強力な抑制機構が存在することを発見しました。この領域の刺激は、除脳動物や正常な動物のいずれにおいても、伸張反射活動を含むあらゆる筋活動を抑制します。局所的なストリキニーネの適用を用いた研究では、延髄網様体腹内側部が前運動野(premotor cortex)からの促進的影響を受けることが示されました。そのため、一次運動皮質の破壊や、脳幹におけるその錐体路の中断は弛緩性の筋力低下を引き起こしますが、前運動野および補足運動野を含むより広範な皮質病変は、延髄網様体腹内側部の抑制機能が低下することによる伸張反射の増強を伴います。
この抑制的影響は、側索の背側半部を通る背側網様脊髄路(dorsal reticulospinal tract)によって脊髄に伝達されます。一方で、背側網様体(dorsal reticular formation)を刺激すると、伸張反射活動を含むあらゆる筋活動が促進または誇張されることが示されています。この促進的影響は、延髄網様体腹内側部の抑制的影響とは異なり、運動皮質による制御を受けません。この促進的影響は、脊髄の前索を通る内側網様脊髄路(medial reticulospinal tract)と前庭脊髄路(vestibulospinal tract)によって脊髄に伝達されます。ただし、前庭脊髄路はネコでは筋過緊張の発展に重要である一方、霊長類ではその重要性が低いとされています。
結論として、動物研究は、伸張反射活動を制御する2つの主要な下行系が存在することを示しています。一方は抑制的な背側網様脊髄路、もう一方は促進的な内側網様脊髄路および前庭脊髄路です。これらのうち、延髄網様体腹内側部(背側網様脊髄路の起点)は皮質制御を受けています。促進系が抑制系を上回る場合、伸張反射が誇張されます。
9. 伸張反射に対する脳の影響: 人間の研究
これらの研究は動物で行われたものと一致する結果を示しました。まず、痙縮は錐体路(pyramidal system)に関連していません。大脳脚レベルや錐体レベルでの錐体路の選択的損傷は、痙縮を引き起こしませんでした。第二に、痙縮は背側網様脊髄路(dorsal reticulospinal tract)による抑制的影響の喪失または低下によって引き起こされます。パーキンソン病を治療する目的で側索の背側半部を切断した場合、痙縮が発生しました。また、痙縮は内側網様脊髄路(medial reticulospinal tract)による促進的影響によって維持されます。
一方で、前庭脊髄路(vestibulospinal tract)の役割は小さいものです。前索内での前庭脊髄路を切断する試みでは、一時的に痙縮が軽減しましたが、恒久的な効果は得られませんでした。一方、内側網様脊髄路および前庭脊髄路の両方を破壊する可能性のある広範な片側または両側前側索切断術は、痙縮を劇的に軽減しました。
さらに、動物研究と同様に、促進的な皮質網様系は前運動野(premotor cortex)に由来することが示されています。実際、内包の前肢(前運動野由来の線維が存在する部位)に小さな病変がある場合、痙縮性の過緊張が関連しますが、後肢(一次運動野由来の線維が存在する部位)に限られた病変では関連しません。
結論として、脳の損傷が痙縮を引き起こすのは、促進的な皮質網様線維が中断されることによって、背側網様脊髄路を起点とする延髄網様体腹内側部が抑制されるためです。また、脊髄の不完全損傷では、背側網様脊髄路が破壊され、内側網様脊髄路が残存する場合に痙縮が発生します。完全な脊髄損傷では、伸張反射に対する促進および抑制の両方の影響が失われます。このような場合、すべての抑制が失われるため、屈曲性痙攣が優勢になります。
背側網様体脊髄路は、前運動野や補足運動野から入力を受けるので、体幹の運動学習が痙縮抑制に関わるかもしれない。体幹の安定性はマスト。
10. 痙縮における脊髄神経回路の変化
背側網様脊髄路(dorsal reticulospinal tract)は、伸張反射を抑制するために脊髄内の抑制性回路を活性化します。一部の抑制回路は、α運動ニューロンの膜に作用して伸張反射の興奮性を低下させます。これらの回路は一般的に「ポストシナプス抑制回路」と呼ばれ、その効果は「ポストシナプス抑制」と呼ばれます。この中には、以下が含まれます:
• 二シナプス性相互Ia抑制(disynaptic reciprocal Ia inhibition)
• Ib抑制(Ib inhibition)
• 再帰性抑制(recurrent inhibition)
また、Ia求心性線維のシナプス前終末に作用する軸索間のGABA作動性シナプスを介して、伸張反射の興奮性を低下させる回路も存在します。このシナプス前抑制回路の活性化は、Ia線維のシナプス終末とα運動ニューロンの膜との間のシナプス間隙での神経伝達物質の放出を減少させ、シナプス前抑制を引き起こします。これらのポストシナプスおよびシナプス前抑制回路は、人間のH反射を用いた神経生理学的技術で調査することができます。
ポストシナプス抑制回路
痙縮患者において、Ib抑制、二シナプス性相互Ia抑制、および再帰性抑制が広範に研究されています。一般に、これらのすべてのメカニズムは痙縮患者で減少していることが確認されており、ポストシナプス抑制の減少が伸張反射の過興奮性に関与していることを支持しています。
シナプス前抑制
シナプス前抑制も、痙縮患者において減少していることが、対麻痺患者や片麻痺患者の上肢で確認されています。
ポストアクティベーション抑制
ポストアクティベーション抑制は、Ia線維からの神経伝達物質の放出を低下させるもう一つのメカニズムです。この現象は、反復的に活性化されたIa線維からの伝達物質放出確率が低下する神経細胞の内在的な特性と関連しています。このため、ポストアクティベーション抑制は抑制性脊髄回路によって媒介されるわけではなく、下降性運動路によって制御されているようにも見えません。
健常者と比較して、痙縮患者ではポストアクティベーション抑制が低下していることが報告されています。また、脳卒中や脳性麻痺の患者において、ポストアクティベーション抑制の低下と痙縮の重症度の間に正の相関が認められています。さらに、脊髄損傷患者では、急性期にはポストアクティベーション抑制は正常ですが、痙縮の発現直前に減少します。
これらの研究は、ポストアクティベーション抑制の低下が痙縮の発展において重要な役割を果たすことを示しています。動物や健常者、脊髄損傷患者を対象とした研究は、ポストアクティベーション抑制の減少が主に四肢の固定によって引き起こされることを示しています。
ポストアクティベーション(Post-Activation) とは、神経筋系において筋肉が一度活動した後に、その活動が一時的に抑制されたり、筋反応が変化したりする現象を指します。この概念は、特に脊髄反射の調節や筋肉の収縮性に関連して研究されています。よって、痙縮筋を使うことで良い変化を促すことができる。
11. 脳および脊髄の可塑性
急性の脳卒中や外傷による損傷の場合、神経学的な障害が発生してから痙縮が現れるまでの遅延は、単なる反射現象ではなく、脊髄および脳で何らかの可塑的変化が起こっていることを示唆しています。
中枢神経系では、不完全または完全な脱神経により受容体が過感受性を持つ現象がよく知られています。この結果として、シナプス後膜の興奮性が増大し、新たな受容体の形成や、脱神経した受容体の形態学的変化が引き起こされる可能性があります。この「脱神経超感受性」の現象は、錐体路からの下降性入力を失ったα運動ニューロンの興奮性増加に関与している可能性があります。
さらに、上位運動ニューロンの損傷後、α運動ニューロンは局所的に成長因子を放出することが知られています。これらの成長因子は、隣接する介在ニューロンからの局所的な枝分かれを促進し、これらの介在ニューロンと脱神経した運動ニューロンの間に新たな異常シナプスを形成する条件を作り出します。この結果、α運動ニューロンの膜上に新しい異常な反射経路が形成されます。
また、脳幹の下降性経路(網様体脊髄路、前庭脊髄路、視蓋脊髄路、赤核脊髄路)が、錐体路の損傷後に運動指令の一部を実行するためにより多く動員される可能性があります。これらの経路は、錐体路に比べて運動ニューロンへの興奮性接続が選択的でない傾向があるため、筋過活動を引き起こす可能性があります。
最後に、重要なメカニズムとして、四肢の固定化によるポストアクティベーション抑制の進行的な減少が挙げられます。これも痙縮の発展に寄与します。
12. 痛みと痙縮
痙縮は痛みの直接的な原因となることがあります。健康な人で、収縮した筋肉を伸長させる(伸張性収縮)と、筋線維の一部が損傷し、それが筋肉の侵害受容器を刺激する物質を放出することが示されています。同様の過程が、痙縮した筋肉が伸張される際にも起こると考えられます。
しかしながら、UMNS(上位運動ニューロン症候群)の陽性徴候および陰性徴候、ならびに軟部組織の変化が、体重の分布を乱し、関節構造に過度の負担を与えることで痛みを引き起こす場合があります。さらに、感覚障害も痛みに寄与する可能性があります。
これらの要因が複合的に作用し、UMNS患者が感じる痛みを引き起こします。さらに、痙縮と痛みの関係は相互に強く影響し合っています。痛みが痙縮を増加させ、それがさらなる痛みと障害の悪循環を作り出す可能性があるためです。
13. 神経リハビリテーションへの影響
このレビューでは、リハビリテーションにとって重要な2つの点を強調しています。
1. 痙縮の中心的な特徴としての伸張反射の誇張
この現象は、伸張反射を制御する抑制性回路(ポストシナプスおよびシナプス前抑制回路)の興奮性が減少することを含む、脊髄レベルでの神経回路の異常な適応に起因します。これらのメカニズムは上位運動ニューロンの損傷の結果です。一方、ポストアクティベーション抑制は、脊髄レベルで伸張反射の興奮性を制御する現象であり、脳からの制御を受けません。この現象は、Ia求心性線維の内在的な膜特性を反映しており、UMNS患者では四肢の固定化により減少します。この固定化は、筋力低下やその他の陰性徴候によって引き起こされます。これが重要なのは、受動的な四肢の動員がポストアクティベーション抑制を回復させ、痙縮を軽減または予防できることが示されているためです。
2. 筋過緊張の原因としての痙縮以外の要因
UMNS患者では、短縮した位置での筋肉の固定化が筋拘縮を引き起こし、これは筋過緊張に大きく寄与します。さらに、筋線維化や筋拘縮の他の要素は、筋伸長中に紡錘求心性線維を過剰に活性化することによって痙縮を悪化させる可能性があります。筋拘縮は、筋肉を長時間伸展させることで予防および治療することが可能です。
結論
UMNS患者では、筋力低下によって影響を受けた筋肉が固定化されます。短縮した位置での固定化は筋拘縮を引き起こし、固有の筋緊張の原因となります。同時に、筋肉の固定化はポストアクティベーション抑制を減少させ、これが痙縮の発展に重要な役割を果たします。したがって、UMNS患者では、影響を受けた四肢の動員と筋肉を短縮した状態で長時間固定化させないことが、筋過緊張を予防および治療する上で最も重要な対策であると考えられます。
この取り組みでは、理学療法が極めて重要な役割を果たします。理学療法は、定期的で個別化されたストレッチプログラムの提供、四肢の正しい位置付け、およびスプリントやキャストの適用を含みます。
2014年度の論文ですが、痙縮に対するアプローチまで言及しています。痙縮はポストアクティベーション抑制によって抑えられていますが、脳卒中によって、この抑制が外れると痙縮として出現するようです。四肢の固定化が必要だということは納得です。痙縮が強い場合は装具が必要。もし装具がなくても、患者さんは自分の力で固定化を作っている。大事なのは正しい位置での固定で、運動を円滑に出来る四肢の固定なんだと思う。